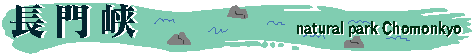
■長門峡の生い立ち
昔、この地球上に人類が、その姿を現わしはじめた頃(今から約50万年くらい前)までは、阿武川は現在見られるような大きな河ではありませんでした。長門と周防の国境に近い木戸山(山口市宮野上・標高542.3メートル)の麓に源を発した篠目川は、東北方に流れ、地福・徳佐を過ぎて石見国(今の島根県)に入り、津和野・日原・青原・横田・高津(益田市の内)を経て日本海へ注いでいました。
その後、突然徳佐の東方に、願成就寺山や三原山が噴出して、川を中央部で完全にせきとめ、しかも火山は一個だけでなく徳佐と津和野との境付近に、大小合わせて7個以上でき、このために、地福・徳佐などの村落は一面に湖水となり、水は逆流して篠生の御堂原付近で、東西両方面からの水が正面衝突し、ここにT字川をつくって北方に流れ、岩石を浸蝕して長門峡の奇勝をつくり、川上村・萩市を経て日本海に注ぐ、今の阿武川となったものだと云われています。
■長門峡探勝と開発の歴史
長門峡の峡谷の美しさは、すでに周知の事実で優雅な反面、豪快な味をもつ大自然の美は、見る人をして飽くことさせませんでしたが、昔は交通の不便なため、わずかに近村の木樵りや、狩人に知られているに過ぎませんでした。
その昔、画聖雪舟がここに来て画筆を揮ったとの伝説がありますが、記録としてあらわれたのは明治32年ごろ、参謀本部陸地測量部員が、この地帯を踏査して実測の結果、この大景観に目のあたり接して、その雄大さに驚いたといいます(5万分の1地形図を作ったのは明治35年6月)。
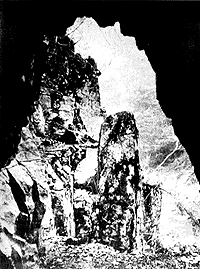
続いて明治41年阿武川水力電気株式会社がダム建設のため峡内を探険し、その写真を人びとに配ったがこれが長門峡を世に紹介した最初のものでした。
越えて明治44年夏には本峡の地形に興味をもつ山口高等商業学校英語教師のエドワード・ガントレット(1,868~1,956・イギリス人)が、御堂原から竜宮淵付近までを自ら踏査し「那馬溪(大分県にある)に劣らぬ景勝地」だとして、「長門那馬溪」と命名して、ひろく一般に紹介するとともに、各方面に、その開発を呼びかけられました。

大正7年、山口線が三谷まで開通、以来、探勝客は急激に増加しました。大正9年、阿武郡長岡村勇二は上京して、南宗画家であり、地質学者の高島北海(1,850~1,931・萩の人・名は得三)をたずね、本峡開発についてその意見を求めました。その年の8月、北海は山根武亮とともに、阿武川上流の「長門那馬溪」を探勝し、高島北海(1850~1913)長門峡図/山口県県立図書館蔵本峡の開発には探勝道路の開さく(鑿)こそ急務であると力説し、これが経費捻出のため、11月長門峡真景100幅画会を結成、村内を始め広く近隣町村有志の協力を得て、北海は自ら細管をふるった長門峡真景100余幅を売却、その代価17,600余円を寄付され、現在の探勝路の基礎が作られました。
大正9年8月10日、長門那馬溪は高島北海によって「長門峡」と命名され、同年10月30日、長門峡仮停車場の営業開始とともに、婦女子の探勝も容易になったので、遠近からの観光客が殺到するようになり、現在もその人気は衰えておりません。
以来長門峡は山口県を代表する渓谷で、全国約30の著名な渓谷にリストアップされ、国および県の「名勝及び天然記念物」に指定されています。

